
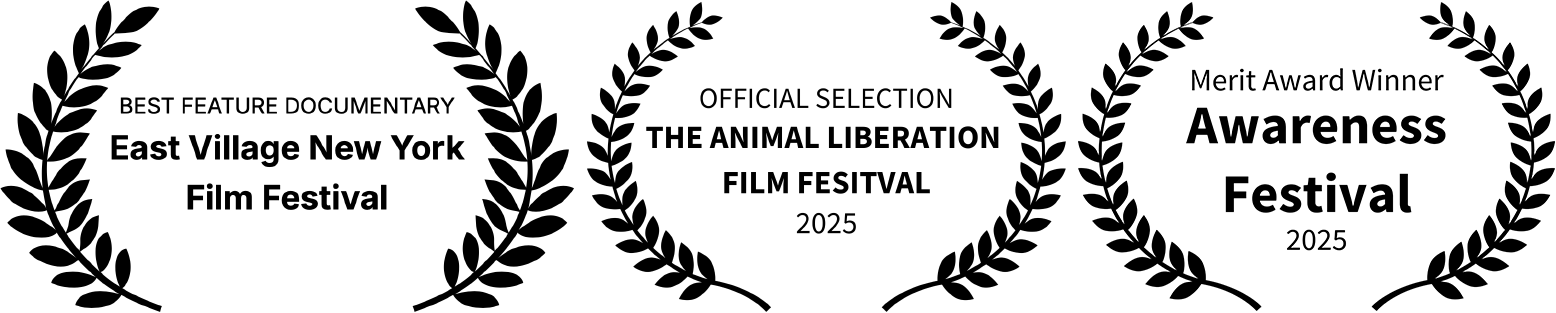






2022年2月から始まったロシアによるウクライナ侵攻。戦争による惨劇が日々報道される中、ドキュメンタリー映像作家の山田あかねは、その現実を自分の目で確かめるため、侵攻から約1ヶ月後にウクライナへと向かった。山田監督はこれまでに、小林聡美主演の『犬に名前をつける日』(2015/監督)や『犬部!』(2021/脚本)など数々の作品で犬や猫の命をテーマに、福島や能登などの被災地への取材を重ねてきた。そんな彼女だからこそ、〈戦場にいる犬たちの現実を伝えなければ〉という覚悟のもと戦禍のウクライナでカメラを回す。そして、一つの動画をきっかけに衝撃的な事件を知ることになる。「戦場にいる犬たちに、何が起きたのか?」─ その真相を探るため、ウクライナへ3年にわたり通うことになった。ナレーションは俳優の東出昌大が務める。自身も保護犬と暮らし、そして猟師として日々命の現場に立つ東出の言葉は、私たちに現実を突きつける。
山田監督は、「犬は人間の最も近くにいる動物。彼らを通して世界を見ると、人間の姿が浮き彫りになる。“犬の向こう側”には必ず人間がいます」と語る。本作では、戦場で生きる犬たちの様子をはじめ、その小さな命を救おうと世界中から駆け付けた人々の奮闘する姿が映し出される。犬たちを取材する中で見えてきたのは、戦争に翻弄される人々の姿、そして様々な立場から語られる平和への願いだった。



東京都出身。テレビ制作会社勤務を経て、1990年よりフリーのテレビディレクターとして活動。ドキュメンタリー、教養番組、ドラマなど様々な映像作品で演出・脚本を手がける。2009年に制作会社「スモールホープベイプロダクション」を設立。2010年、自身が書き下ろした小説を映画化した『すべては海になる』で映画初監督を務めた。その後、東日本大震災で置き去りにされた動物を保護する人々を取材したことをきっかけに、監督2作目として『犬に名前をつける日』('15)を手がける。2021年には、青森県北里大学に実在した動物保護サークルを題材にした映画『犬部!』では脚本を務めた。2022年2月24日に起きたロシアによるウクライナ侵攻から約1ヶ月後、本作の取材を開始。その最中で、飼い主のいない犬や猫の医療費支援をする団体「ハナコプロジェクト」を俳優の石田ゆり子と創設した。現在は、元保護犬の愛犬“ハル”と暮らす。

埼玉県出身。モデルとして活動後、2012年に映画『桐島、部活やめるってよ』で俳優デビューし、日本アカデミー賞新人俳優賞などを受賞。2013年、NHKの連続テレビ小説「ごちそうさん」に出演し注目を集め、俳優としての知名度を確立。続く2014年の『クローズEXPLODE』で映画初主演を飾る。その後、映画やドラマ、ナレーションなど様々な映像作品に出演する。主な出演作品は、『寝ても覚めても』('18)、『コンフィデンスマンJP』シリーズ('19〜'22)、『BLUE /ブルー』('21)、『Winny』('23)など。また、狩猟免許と猟銃所持資格を取得しており、2024年には自身の狩猟生活に1年間密着した初のドキュメンタリー映画『WILL』が公開された。現在は、愛犬“しーちゃん”と一緒に山での生活を送っている。
Comment
可愛い犬の映像がふんだんに映し出されます。はしゃいでは見せるその純真無垢な表情に、戦禍が続いている事を忘れそうなほどに。
犬は人間に助けを求め、時に癒し、稀に人間よりも悟った顔をします。
犬から考える平和について。
犬は当たり前の幸せを享受出来る、素直な生き物。 犬から”だから”考えられる平和について、の映画とも言えます。
広島県出身。作曲家、音楽プロデューサー。大学卒業後、数々のCM楽曲を手掛け、2008年に短編映画『BABIN』の音楽を務める。その後、石井裕也監督作『舟を編む』('13)で、第37回日本アカデミー優秀音楽賞を受賞。その他、主な代表作として、細川徹監督作『オケ老人』('16)、中野量太監督作『湯を沸かすほどの熱い愛』('16)、永井聡監督作『帝一の國』('17)、今泉力哉監督作『his』('20)、石井裕也監督作『愛にイナズマ』('23)、荒木伸二監督「ペナルティループ」('24)など、数多くの映画音楽を担当している。


ITの力で飼い主と犬と猫をつなぐためアニマルIDを独自で開発。ウクライナの侵攻後、シェルターや医療機関と連携しアニマルIDを無償で提供、その数は一ヶ月で5万を超えた。現在は、大学生の息子とウクライナに残り活動を続ける。

ウクライナ侵攻が始まってすぐに、国境近くでペットを連れた避難民の救助活動を開始する。ウクライナで被災した犬と猫のために、メディカにある農場を借りて臨時シェルターを設置した。ボロディアンカのシェルターで救出された犬の一部を引き取った。現在はポーランドの本部に戻り、馬を中心に多くの動物たちの世話をしている。

キーウ市ボロディアンカにある動物シェルターでボランティアとして犬の世話を担当。侵攻後閉鎖されたシェルターに、ロシア軍が撤退した翌日に駆け付け、生き残った犬250匹以上を救出。また、カホフカダム爆破による洪水で被災したヘルソン市にもフードや医療品などの物資を届けるなど被災地支援を続ける。

一時期ロシアに占領された激戦地・ヘルソン市出身。現在はキーウに避難しているが、ヘルソン市が水没してすぐ、故郷に向かう。道中で見つけた野良犬にフードを与えたり、ロシア軍が対岸に迫る地域で、子犬を救うなど積極的に活動を続ける。

イラクやアフガニスタンに従軍していた元・イギリス軍兵士。退役後に、動物救助隊「BREAKING THE CHAINS」を立ち上げ、戦地や最前線で動物の救出活動を行なっている。ウクライナの他に、パレスチナのガザ地区でも活動している。また、自身が重度のPTSDを抱えていた時期に犬に救われた経験から、戦争で負傷した兵士に向けたドッグセラピーを実施している。
自分の命は惜しくないという。動物の命を助けることが自分の人生だと。
戦禍の中に分け入って小さな命を救うために自分の命を捧げているひとたち。
戦禍にもかかわらず保護犬を引き取るウクライナのひとたち。
「人間には愛が必要だから」と。
そんなこの世で一番尊いことを、この映画は私たちに語りかける。
空を飛ぶのは戦闘機でなく鳥であれ。地を走るのは戦車でなく犬であれ。
同じ人間が平然と無差別に虐殺を行う一方で、戦地に真っ先に飛んで行き動物たちを助ける人がいる。
死者数が何万何千と漠然と「数」になる世界で、ウクライナのシェルターで命を落とした犬たち一匹一匹を、泣きながら名前で呼ぶ人たちがいる。
一人一人、一匹一匹に名前があり、誰かを愛し、愛された命だったということが新たに心に刻まれ、私たちを突き動かす。
戦地や被災地で、危険をかえりみずペットを救うという無償の活動をする人々がいる。なぜなら、ペットは無償の愛と信頼を人間に寄せてくれるからだ。
それにしても、なぜ、日本の被災地ではペットを連れた避難ができないのだろう?ペットも大切な家族の一員だというのに。
戦争により行き場を失った動物たちの命を救うことで、実は戦争により傷ついた人々が救われている──その事実に心震えた。既存のニュース映像やSNSでは目にできない、強烈な愛と生命力がつまった映画。
戦争で犠牲となるのは人間だけではない。人間が起こした戦争によって、動物も苦しみ、無惨に命を落とす。テレビメディアが伝えることのない、動物の犠牲がある。その死を悼む人々と、命がけで動物を救う人々の、尊い活動と勇姿に胸を打たれる。 なぜ動物を救うのか、その大切な意味と価値を知ってほしい。
人命が優先されるのは仕方ないかもしれない。
けど犬も心に傷を負う。
"かわいそう…"で終わってた先の一歩、自分に何ができるかを考えていきたい。
命の価値をあげるのも、動物を守れるのも人間であることを、この映画から考えていきたい。
犬の視線を通して、悲惨な戦禍や人間社会の苦しみが浮き彫りになってくる。生き抜く犬たちの姿は、まさに人間社会の鏡像なのだと感じた。
この映画は、大きな流れを止めることは難しい中でも、身の回りの命を救うことを諦めなかった人々の物語である。またその人々に向き合ったさまざまな境遇の犬たちの物語でもある。その事実は、このロシア・ウクライナ戦争の中の出来事の一つとして、多くの人の記憶に留められるべきだろう。
映画の中に写る動物の中で、人間だけが悪魔に見えて、天使にも見えた。
きっと、その両者が個人の中に共存しているのが人間なんだと思います。
「自分の命が危険でも動物を救いたい。私の生きる理由なんだ」
戦場で動物の救出活動を行なっている元兵士トムの言葉。
ただただ両者の間で右往左往するのではなく、自身の生き方を選ぶことができるという可能性に唯一の希望を感じました。
自らの生命をギリギリまで危険にさらして犬を救う人たち、
それを記録して、誰かに届けようとする山田さんの熱量にひたすら圧倒されながら、
その熱に反応する回路はいったい自分の中にあるんだろうか、
とまた自分のことばかり考えていました。
自分と、犬との距離。
ウクライナとの距離。
ガザとの距離。
解雇されたシェルター所長との距離。
自分ごとにできるのって、距離だけの問題なのだろうか。
でも、知っている山田さんがウクライナで動いている姿には、
自分にとって、これまでに観たどのニュース映像とも違うインパクトがありました。
きっとこれも距離ですね。
届くべき人に届きますように。
動物と人間が共存する事は、結局のところ人間側の都合なのかも知れない。
災害時や戦争と言う有事の折に、当たり前に優先されず皺寄せを受ける動物達の姿に、自分を含む"人間"と言う生き物の哀しき本質を見てしまう。
しかしその戦時下にも関わらず、自身の危険を顧みず戦地にて動物を救おうとする人達がいる。
山田監督を介し彼ら彼女らの存在や活動を知れた事は、動物を愛する者として、人間として、希望でしかない。
果たして自分には何が出来るだろう。
それを具体的にしたいと強く思った。
遺言を書いて戦地に赴き、命懸けで本作を作った山田あかね監督。
心から尊敬致します。


ナレーションを引き受けるにあたり
―― 本作のナレーションを引き受けようと思ったきっかけを教えてください。

東出 配給会社のスターサンズさんはこれまでに素晴らしい社会派の映画を多く輩出している映画の制作会社だと思いますが、今回の作品のように日本から海外に人が赴いて撮影するドキュメンタリー映画を制作している印象がなかったので意外でした。そして、戦争についての話であるというのは理由として大きいです。戦争は、人類がずっと続けてきている悪行だと思っています。それを扱うドキュメンタリーなら見てみたいし、その上、監督たちと気持ちが一つなら、ナレーションも引き受けたいと思いました。
あとは、僕も長いこと犬猫を飼ってきて、やっぱり彼らが好きなんです。だから、ウクライナの戦地の犬を撮った映画だと言われたら、絶対自分は好きだろうなと思って手を挙げました。
―― 実際にナレーションを収録して、どのような心境ですか?
東出 自分は役者をやらせていただいていますが、世界には運命に翻弄されて困っている方々も実際にいるわけですよね。そんな方々の助けに少しでもなるような企画に携われるのは、役者冥利に尽きると思います。やらせていただいて良かったです。
犬と人間の関係について
―― 犬を飼われていますが、どのようにして絆を深めていますか?
東出 昨日も、今飼っている犬の〝しーちゃん〟に「しーちゃん、こんなに仲良くなると思わなかったね」って言いました。しーちゃんは普通に白目をむいて寝ているだけなんですが。そんな言葉を1日100回くらい言っています。これが人間同士の関係だったら、こんなに愛情を垂れ流すことはできないですが、しーちゃんには愛を素直に伝えられます。
動物と人間の境目をこれとは決めていないですが、動物の方が直情的だったりしますよね。だから、僕の周りに駆け寄ってきて食べ物の争奪戦になったりすると、同じ目線で「コラッ!」って怒ったりもしますね。
―― 本当の自分を表せるのは、犬に対してと人間に対してでは違いはありますか?

東出 とある本に書いてあったのですが、長い歴史の中で犬はコンパニオンアニマルといって、人間の相棒のような存在だったそうです。僕も、犬は弱者ではなく人格のようなものがあって、人間と対等な立場だと思っていたので、その考えには納得しました。本当に心から無邪気に通じ合えるという存在は、人間より動物の方が多いかもしれないですね。人間でも自分の子供や家族に全幅の信頼を置いているのは間違いないですが。
人間こそ犬から学ぶことはたくさんあると思います。犬は将来のことに思い悩んだり、鬱になることはあまりないんですよね。今の環境が辛い時は、食欲がなくなったり、痩せたりすることはあると思いますが。でも、その日暮らしで食べてそれに感謝して生きている犬ってすごいなと思います。人間はお腹いっぱいで幸せでも、将来を不安に思ったり人間関係で悩んだりしますよね。でも、犬はそうならないので、動物ってすごいなと思いながら生活してます。なんだか心が熱くなっちゃうな。
山田 人間は、約1万5000年前から犬と一緒に暮らし始めたと言われています。世界中のあらゆる場所で、国家・宗教関係なく同じぐらいの時代に、みんなが犬と暮らし始めた。例えば馬や牛の場合、食べるためや移動のためという目的があるけど、犬と猫に関してはそこまで人間に利益はないんですよね。最初は狩りを手伝ったりしていたと思いますが。北海道の旭山動物園の元園長・小菅正夫さんが「人類は身近に犬がいたことで、自然とのつながりを保ち、精神的破綻を起こさずにすんだ」と言っているんです。近くに小動物がいなかったら、人類はとっくに精神的破綻によって絶滅していたのではないかと。私もそう思います。人間が大変な時に、生きる支えになる存在が近くにいることがどれほど人を救うのかと。それは、今回の戦争も同じなんだと思いました。
人が失ってしまった何か隙間みたいなのを埋めてくれるものがありますよね。兵士のためや刑務所などでもドッグセラピーが行われてますが、壊れた人間を救うには本当に動物が大事な存在なんだと。今回取材した元軍人のトムもPTSDから救われたのは犬のおかげだと言っていました。動物の持つ力っていうのは、 毎回すごいなと感じます。
東出 犬猫やペットを飼ったことのない人に、犬が家族になると言っても「なにがいいの?」って思われるんですけど、家族や愛おしい人って、代替が効かないんですよね。仕事で褒められたとか、なにかいい物を得られたという時は、一時的に興奮が絶頂に達するんです。これがドーパミンですけど、ドーパミンには中毒があって、どんどん欲しくなるからキリがないんです。でも、日光浴をした時に出るセロトニンや、犬や猫をぎゅっと抱きしめたときに出るオキシトシンと言う脳内伝達物質は、恒久的に、生きてて幸せだなという気持ちになれる。これは仕事のドーパミンとは違いますよね。仰る通り、動物と一緒にいて救われることや、動物から学ぶことがあるんじゃないかなと僕は日々思ってます。
日本と海外の動物愛護について
―― 野良犬が街で暮らしている様子は日本では見られない光景ですが、海外で遭遇したことはありますか?
東出 人間は、あらゆるものに対してそれぞれの価値観を持っていると思うんです。例えば山の中で犬が走り回っている姿は、僕はすごく好きな光景ですが、犬が脱走した時に危機感を抱く人はいます。お国柄もありますが、日本はどうしても同調圧力とか、こうあらねばならないという模範や規範みたいな常識がありますよね。でも、ニューヨークを歩けばセントラルパークでリードをつけている飼い主なんてほとんどいないし、パリではあんなに交通量が多くてもノーリードで歩いていたりするんです。南米では多くの犬が去勢していて、狂犬病がほとんどない。そこら辺に野良犬がいるけどみんな上手いこと車に轢かれずに生きていて、可愛いねって言うとすぐ寄ってきてくれる野良犬天国ですね。だから、去勢手術という対策をしながら野良犬を放し飼いするというウクライナの環境は、犬好きの僕にとっては幸せです。
ただこれは難しくて、100匹いたら1匹ぐらい車に轢かれてしまうかもしれません。でも、生きるっていうのはいつか死ぬっていうことで。今の日本の子育てしかり、ペット文化もそうかもしれないですが、この子が生きながらえるためにといってガチガチにゲージから出さなかったら、その子は幸せなのかってわかんないじゃないですか。危険も伴うけど路上でのびのび生きるという喜びもあると思うんです。死んでしまうかもしれないという残酷さも覚悟しながら、享受しながら生きていく人生にこそ喜びがあると思ったりもします。
―― 日本と海外の動物愛護について、どのように感じますか?

東出 難しいですよね。結局みんな好きだから故にその思想が偏っていると思われたりしがちなのではと思います。日本だって30年前、野良犬が肉屋の前にいたらその肉屋の店主は足蹴にしてたと思うんです。でも今、野良犬を足蹴にする人って日本国民の中でもほとんどいないですよね。そう考えると、野良犬でも動物に対するアニマルウェルフェアとかリテラシーみたいなのが上がっているのかもしれない。この権利や思想みたいなものが行きすぎると、排他的になったり、 他者に対して攻撃的になったりするのだと思います。だから、古き良きルーズさも必要だし、慈しむ心もみんなが持って、正解は1つじゃないって思いながらやっていくことが大切なんじゃないかなとは思うんですけれども。
山田 いま東出さんが仰った通り、動物愛護って正解は1つじゃないということがすごく大事なんですよね。猫は絶対家から出すなとか、犬はリードを絶対離すなとか、そういう正解のルールみたいのを作っていくとすごく苦しくなっちゃう。でも、どうしても正解を作りたがる傾向にありますよね。本当に動物が幸せかどうかって、私たち人間は動物の気持ちはわからないですよね。絶対に正解ってわからないんですよ。
動物の命について
―― 東出さんの山での生活は、生と死が隣り合わせだと思いますが、本編に出てくるような人間と動物が共存する町の暮らしはどのように映りますか?

東出 そうですね。 人は生きている限り何者かの犠牲の上に生命を存続させられるし、あらゆる動物がそうだと思うんです。動物を殺したくないという意思から菜食主義になる方もいますが、それが悪いということではないです。例えば、ガソリンを使ったり、化粧品や薬品を使ったり、こういう衣類を着ていようが、
何か環境を汚染しているということはある。また、猟師がそういう害獣とされる獣を殺すから食卓に肉が届く。それをみんなは知らないということではなく、どのタイミングでどういう生き方を選択するかは人それぞれだから、他者を責めようとは僕は思いません。それほど死というものが近くにあるんだなと実感を得ています。なんか死とか生というもの、今回の台本にもありましたが、命の重さって種族によって違うからいいなと思っていたら、あまり人を攻撃しようと思わなくなりました。それが今の状態です。
例えば鹿は、今獲っても9割ほど捨てられてるんです。焼却処理施設で燃やしたら、化石燃料を使ってただ炭化させるだけなんです。そして、それは山の中に放置しちゃいけないと法律上決められています。でも、山の中に放置すると他の動物の食べ物になるんですよね。だから、獲ったものを自分たちが食べたい分だけ食べて山の中に放置することは、別の動物を生かすことにも繋がるんです。動物の1体2体で疫病が流行るわけでもないですから。こういう循環の中に生きていたいなと最近は思ってますね。
山田 東出さんのドキュメンタリー映画『WILL』の中で、鹿を撃つ時に何回撃っても慣れなくて、その子をかわいそうだと思ってしまうと話していましたが、それは今もそうですか?
東出 今もそうですね。でも、おそらくプロの猟師の方はいつしかそう思わなくなるから、自分もできるようになるのかなと思いますけど、今は変わらないですね。でも、その痛みで辞めようとはならないです。僕はそれでも動物が好きだし、だから近づきたいという気持ちもあるんです。
『アクト・オブ・キリング』というドキュメンタリー映画で、昔自分がどうやって人々を殺してきたかを戦争自慢のように話す男性がいるじゃないですか。その人、本当に最後に、蓋をパカっと開けたようにわーっと号泣しますよね。猟師の人でも、そんなこと思っちゃいけないと言ったまま棺桶に入る人もいるけど、やっぱり動物が好きだったりするんですよ。そういう人たちも、本当の心の蓋を開けたら、こんなに殺したのかってなると思います。だからそれは一緒だと思います。でも、僕の狩猟の師匠も、僕も、蓋を開けっぱなしにしたまま生活するんですよ。だから、今でもうわって思っちゃいます。

山田 それって辛くないですか?
東出:辛いです。辛いけど、動物が好きだから辛いって言って蓋をしようとするのは、この子たちに対して申し訳なさすぎる。それこそ、「おまえ自分がどんだけ偉い存在になったつもりなんだ」って自分のことを嫌いになってしまうと思うんですよ。母鹿を撃って、子鹿がピーピー鳴いてて、「お母さんこっちだよ。なんで来ないの」っていう声を背中で聞いてたら、やっぱり僕は蓋を開けたままだから「辛いけど、この肉をうまい肉にしよう」と思って持って帰ります。そして、「うまい」と言って食べている時に、やっぱ生きてるっていう実感とありがたいという気持ちが沸きますね。
山田 今は肉とか食べても、殺しているところを見ないで済む社会のシステムになってますよね。だから、痛みを感じないように、すごく丁寧に作られていますね。東出さんはそこに立ち向かっているところがすごいなと思ってます。というのも、私がこのボロディアンカで起きた映像を、人に見せると、残酷だからあまり死体を見せすぎない方がいいんじゃないかという話も出ます。だけど、こういう残酷な死骸があったってことを伝えないといけないと思います。そこにいた犬たちが本当に死んだんだってことを隠してしまうと、柔らかくしか物事を見れなくなる。傷つくかもしれないけど、死んだ子のためにも彼らの死を認めて、受け止めてあげないとダメなんじゃないかと思ってます。死を見せないと死ということがわからないのではと。それは嫌なものだし、見たくないじゃないですか。でも、犬も生き物で、殺処分も含めてどこかでみんな死んでるわけだから。毎日見なくてもいいけど、1回は見ておこうと。例えば戦争の端っこでは犬とかもいっぱい死んでますということは、1回は見ておいてほしいと。重いですよね。でも、ずっと見るのは辛いと思うからこそ、東出さんみたいに現場で毎回見続けるっていうのは、動物好きにとってはすごいことだなと思います。
東出 いや、まだいつ猟師をやめるとかいうのもまだわかんないです。いつかもう無理だと思ってやめることがあるかもしれないです。まだまだ考えることがいっぱいあるし、しばらくは逃げないで考えたいなって思います。
本作を通して感じてもらいたいこと

東出 僕がこの映画を見た時に思ったのは、こういう戦争や動物がテーマの作品は、嫌な言い方をしてしまうと“お涙頂戴”に作られがちですよね。でもこの作品は、監督の犬愛が溢れているから犬のシーンがとても長いんですよ。ナレーションをあてた後に、ちゃんと映像に収められている犬が嬉しそうにするんです。で、この犬の嬉しそうな姿は犬好きはずっと見ていられるし、犬の嬉しそうな顔とか、希望を抱いてる顔というのは世界共通なんだなと思います。 だから、うちの犬も、日本のその辺を散歩してる犬も、ウクライナの犬と変わらないというところを感じてほしいです。ちゃんと可愛い犬が映ってるし、犬を愛でに映画を見に来てもらえると良いですね。当事者意識というのは少し仰々しいですけど、そういうところから一緒に物語を感じてもらえたらいいのかな。少し離れたところで起きていることを想像してもらえたらなと思います。























Comment
戦禍のウクライナ、首都キーウで起こった犬をめぐる「ある事件」。
その一部始終を捉えた映像を見た私は、彼らに…犬たちに何が起こったのか知るために、3年にわたり、ウクライナに通った。そこで見たのは、「戦争の悲惨さ」だけでなく、極限状況のなかで、犬や猫、動物たちを救おうとする人達の「強さと優しさ」だった。
戦争という悲劇のなかで見た、ひとすじの希望の物語です。